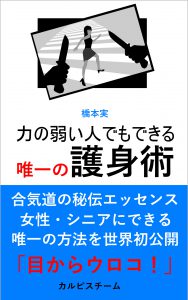皆さん、お元気ですか?
私はとても元気です。
しばらくブログをお休みにしていましたが、実はその間に、護身術の本を書いていました。
そして、アマゾンのキンドル版で出版しました。
本の題名は
「力の弱い人でもできる唯一の護身術
-合気道の秘伝エッセンス
-女性・シニアにできる唯一の方法を世界初公開」
としました。
先月6月9日に、東海道新幹線で無差別殺傷事件が発生し、誠に残念なことに一人の男性が亡くなりました。
その男性は、頭もずば抜けていて、会社からも期待されている上、周りの人にやさしく非常に正義感が強く本当に人格的に優れた人だということでした。
また、刃物をふるう犯人に無防備な素手で相手に立ち向かうというのは、並外れた勇気の持ち主であったのでしょう。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
でも、本当に残念でしかたがないのは、もし少しでも日ごろから護身への問題意識があれば貴重な生命を失うことがなかったのではないか思われる点です。
この悲惨な事件から分かることは、日ごろの護身の意識がなければ、このような東大を出ているほどずば抜けて頭がよくても命を失ってしまうという点、普通の頭しかない私たちは、それこそ日ごろから十分注意しておかなければいけないという点ではないでしょうか?
ところが、マスコミでは視聴率の関係からか、こういった事件が起こっても全く護身について語られることがありません。
そこで、そういった悲惨な事件をこれ以上増やさないためにもと、安全確保を重視した護身術の本の必要性を感じ、この度、出版することにしました。
本書の大きな意義は、本来は合気道の一部の者だけが独占していると思われる力のいらない秘伝技術の本の一部ですが公開した点です。ですから、合気道修行者も非常に参考になるとは思います。
本書で書いた技術は、骨の技術の秘伝、皮膚の技術の秘伝、空間感覚の技術の秘伝の本の一部を護身に焦点を当てて書いたので、実際に合気道の技に活かすには不十分とは思います。
何故なら、素人の護身という点で書いていますので、秘伝技術の幅広い応用については言及していないからです。
それでも、力のいらない技術の一端を知ることができると思いますし、秘伝技術の説明ではイラストなど入れて分かりやすくしたつもりですので、ご興味がある方は読んでいただくといいと思います。
また、一般の人も、今後このような犯罪がますます増えると思いますので、是非とも安全確保のため読んでいただければ幸いです。
現在のところ、価格は250円としています。
しかし、このことを当会の会員の皆さんに話したところ、「安すぎる」と言われました。そこで、今後の値段を再考しておりますので、急遽上がるかもしれませんがあらかじめご了承ください。
なお、価格を変更する際は、ブログでお知らせいたします。
以下にアマゾンのリンクを貼っておきます
力の弱い人でもできる唯一の護身術
-合気道の秘伝エッセンス-女性・シニアにできる唯一の方法を世界初公開