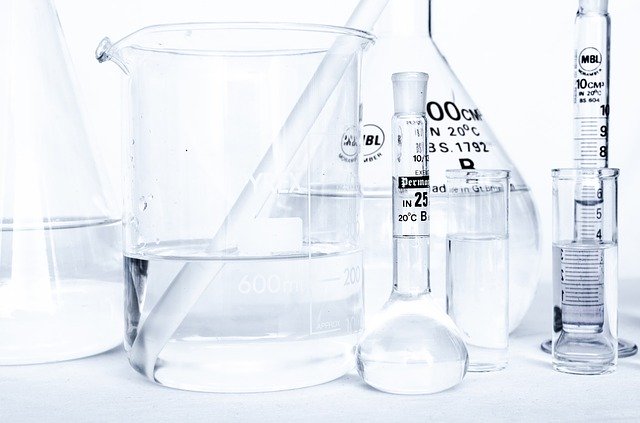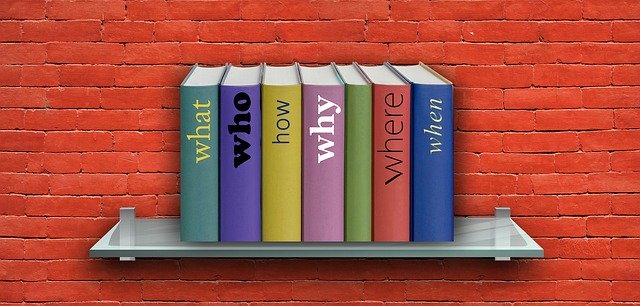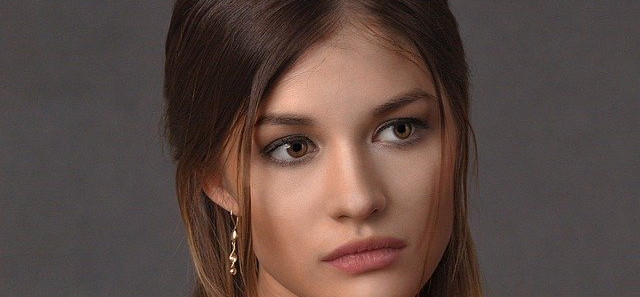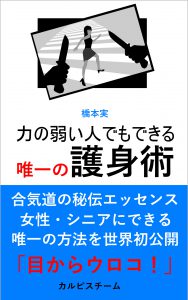皆さん、お元気ですか。僕はかなり元気です。
さて、今日は、仏教の瞑想法に止観というのがありますが、この考えは、合気道で相手との関係を成り立たせるのに非常に共通するものだと思っているので、今日はそのことをシェアしたいと思います。
止観
仏教の瞑想法で止観というのは、2つ瞑想法を指したものです。仏教では瞑想を止と観の2つに分類します。
止とはサンスクリット語ではシャマタといい、心の動揺をとどめて本源の真理に住することしています。
また、観とはサンスクリット語ではビパシャナといい、 不動の心が智慧のはたらきとなって、事物を真理に即して正しく観察すること であると言われています。
このように説明すると非常に難しいので、もう少し簡単に説明すると、止とは心を一点に集中させて、全く散乱させないことで、観とは現前の境界を離れて、様々な想いを巡らすことです。
言い方を変えると、止は一点集中、観は広い集中ということができると思います。
ちなみに、止というのは、禅宗の禅のことです。天台仏教では魔訶止観といって2種類の瞑想を行っていましたが、止だけを行う仏教の一派が禅宗となったようです。
合気道での止と観
合気道では、相手と一体になるようにとよく言われます。
単に、相手と一体になるというだけでは、色々な誤解が生じます。
例えば相手と一体になるといっても2種類考えられます。
- 相手中心の場合の一体
- 自分中心の場合の一体
そしてよく誤解されるのが、合気道は相手に合わすのだから、相手中心の一体で、相手があって自分があるという立場をとることです。
この場合、自主性をすべて放棄し、相手に任せることになります。要するになすがままになるということです。これでは自分を守ることはできません。
合気道は、自分が中心です。こういうと自己中と思われるかもしれませんが、全くその通りで、自分が中心になって相手を思うようにするのが合気道の一体です。
そこで、開祖は、合気道は引力の錬磨であるといわれています。
これは、自分が宇宙の中心になり、自分の引力で相手が自分に吸収され、ついには一体となるということになります。
それで、まず自分の中心を決めることが大切です。これが止といえます。宇宙の中心である自分の中心は不動とするわけです。
そして、引力により相手が自分と一体となり、相手もまた宇宙の一部とするわけです。
これが合気道の一体です。このとき、自分の中心から、意識を広げ自分を取り巻く空間、さらには相手へと広げていいくわけです。
この発想が我即宇宙という合気道の考えであり、宇宙の気と一体となるという考えです。
そして、面白いのは、単なる思想だけに終わらず、この考えが合気道の形の中に活かされています。
もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。
にほんブログ村