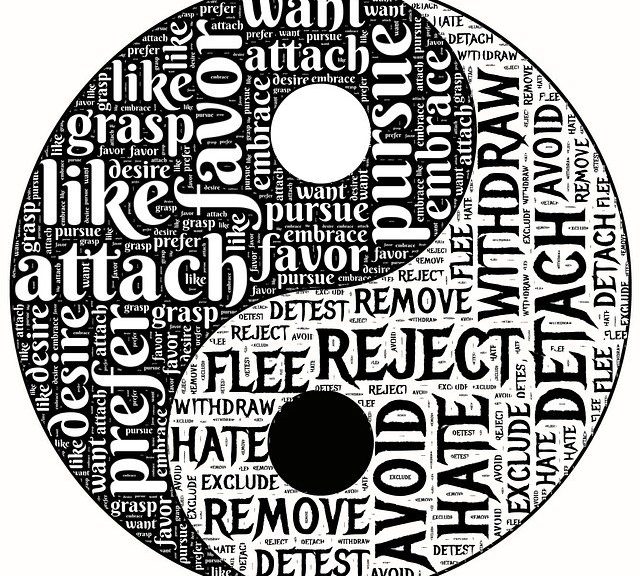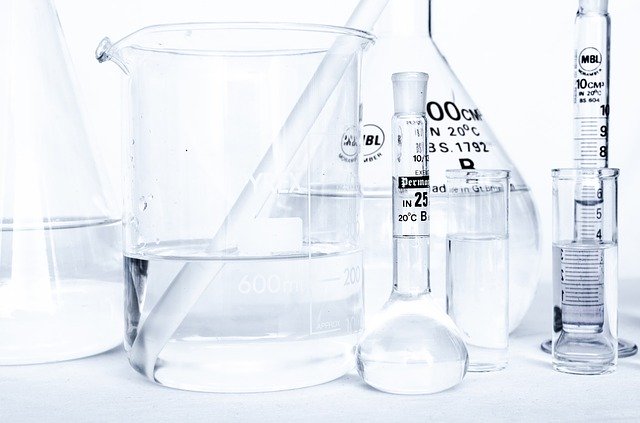皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。
さて、師匠は合気道の極意は呼吸力・気の流れ・螺旋形とおっしゃいましたが、今回は気の流れと螺旋形について話したいと思います。
螺旋形でぶつかりを無くし先をとる
相手と対立する場合、普通人は最も力が入るところで対立をします。
そうすると当然筋力が優勢な方が勝つことになります。
合気道では相手との調和を重んじるということですが、合気道が武道である以上、それと同時に「先」を取ることが大切です。
先とは、先手を取るということですが、相手よりも先に優位に立つということです。
しかし、体力が劣勢なものが、体力の優位なものから先を取るとなると、非常に難しいものです。
そこで、合気道は相手と調和しながら、先を取る技術である「螺旋形」を使います。
螺旋形というのは、移動しながら円運動を描く軌道を取りますから、円運動で相手の方向を変えながら、前に進むことができるわけです。
気の流れとは集中空間の持続
螺旋形の指導を行ったとき、多くの人がやるミスがあります。それは、対立が起こっている点を螺旋で逸らすと、そこで満足してしまうことです。
そうすると、またさらなる対立ができます。そしてまたそこで螺旋で逸らす。という繰り返しを行ってしまいます。
しかし、螺旋の流れができると途切れず、そのまま流れるように進んでいくと、相手に付け入る隙を与えず、技を進めていくことができます。
それが気の流れというものです。要するに、気の流れを起こっているときは、ゼンマイの時計のように、針が動き続けていることで、クウォーツの時計のように針が一秒ずつ止まったり動いたりしないことです。
そのため、常に左右の手のバランスを考え、左右の手に常に意識をもっていくことです。これが観という考えかたです。右手をつかったら左手、今度は右手というのように、意識を切り替えません。
言い方を変えると、観によってつくった自分の空間を持続することと言えます。そしてこの空間が宇宙の中心と感じることで相手は不思議と逆らえなくなります。
気の流れ、合気道では非常に大切な考えです。
もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。
にほんブログ村