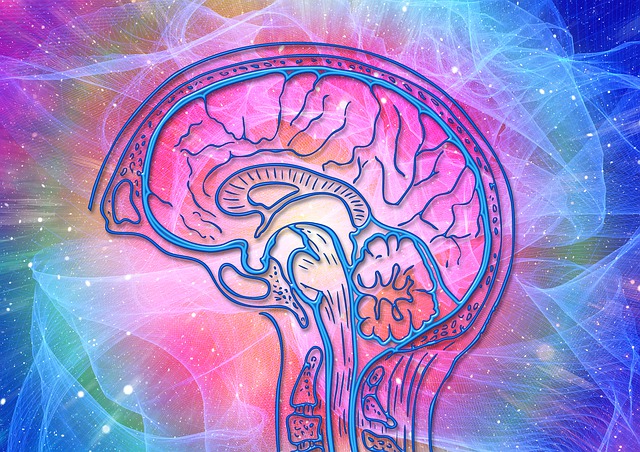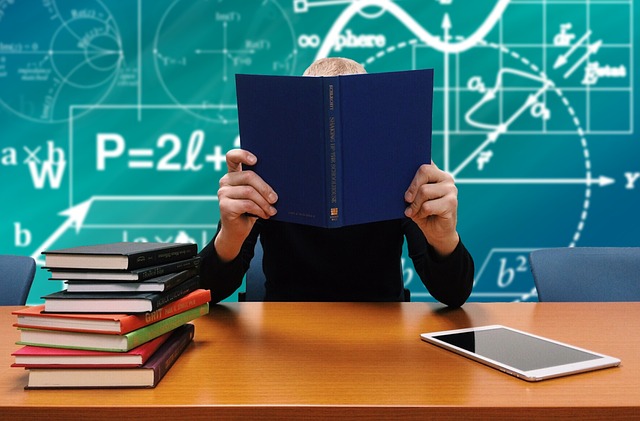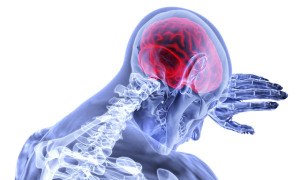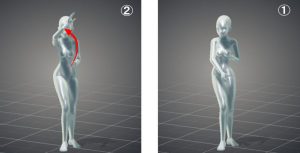皆さん、お元気ですか? 僕はメチャクチャ元気です。
さて、実は僕は今Next NLPという心理学のセミナーを受けるために東京に来ています。
前回の内容を読んだ人は、なぜこのようなセミナーに参加したのかご察しがつくと思います。
このセミナーに参加した理由は、僕が指導している護身術で、もっとも難しい空間感覚の技術をより分かりやすく説明できるように幅広い知識を身に付けヒントになる素材を探すためです。
Next NLPとは
NLPとは 脳神経言語プログラム(Neuro Linguistic Programing)の略称です。別名を「脳の取扱説明書」とも呼ばれる心理学です。
NLPとは、1970年初頭に心理学部の生徒であり数学者だったリチャード・バンドラーと言語学の助教授ジョン・グリンダーによって開発されました。
当初は、開発者の地位の問題もあり、NLPは世間からまったく見向きもされませんでしたが、世界一のコーチの一人であるとアンソニーロビンズが、蛇恐怖症の人から短時間で恐怖を取り除くという変化を公開の場で起こしたことにより、世界に急激に広まったものです。
ところが、NLPは神経言語プログラムといわれるように、コンピュータにはプログラムを組むための言語がありますが、NLPは人間に対するプログラム言語に相当します。
パソコンが世に出始めたころ、Basic言語で、ユーザーが自らプログラムを組む必要があった時代、一般人がなかなか手が出せなかったのですが、NLPもそれ単体ではかなり厄介なものです。
ところが現在は、パソコンであれば便利なアプリがあり、誰でもすぐにパソコンを使いこなせるようになります、Next NLPは、パソコンでいえばアプリに相当するもので、一般人でも学べばすぐに使えるようにしたものです。
セミナーで学んでみて
では、実際セミナーで学んでみたところどうだったかというと、合気道で非常に参考になるスキルがありました。
あまり詳しいことは公開の場では言えないのだけれど、それは「センターをとる」スキルです。
センターをとるスキルというのは、自分に尊厳をもたらし、自分の生きる価値を自分自身に確認させ、周りから何を言われてもぶれない自分を作るものです。
実は、合気道にも「天の鳥船の行」というものがあり、その中の振り魂(ふりたま)と呼ばれるやり方で井口師範から受けた秘伝と非常によく似たやり方でしたので本当に驚きました。
合気道の秘伝では、スキルで得た感覚を実際の技を行う上で使います。
一方、Next NLPでは自分の尊厳を確立するのに使いますので、本来の神道の儀式であった意味がこのセミナーに参加してはじめて実感できました。
もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。
![]()
にほんブログ村
また、上の「コメントをどうぞ」をクリックして、いいね!してもらえるととても嬉しいです!