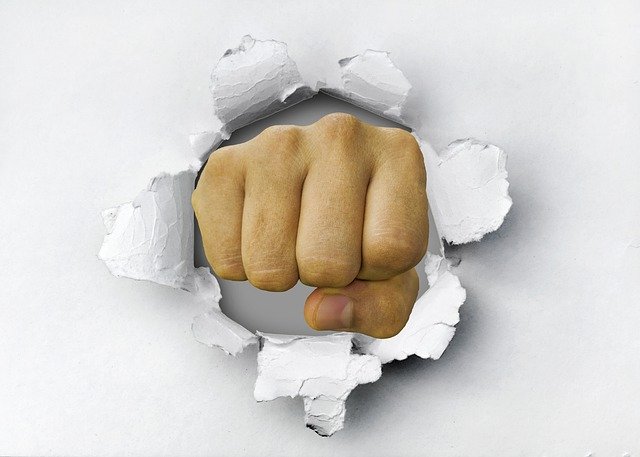皆さん、お元気ですか? 僕は相変わらずメチャクチャ元気です。
さて、前回は結びということについてお話ししました。
武道の目的は、元々は襲ってくる敵を撃退することにありました。一方、合気道の前提は相手を受け入れることにあり、合気道は、武道であるため、ここに大きな矛盾があり、全国の合気道の道場ではその矛盾に対してさまざまな考えがあるという話が前回の話でした。
今回は、僕の師匠の井口師範のこの矛盾点の解決をどう解消したかという点についてお話しします。
合気道は自然でなければならない
井口師範は「曰く、合気道は自然でなければならない」と言われました。
井口師範の言われる自然とは調和のとれたことです。そのため、「ああしよう、こうしようと思ってはいけない」とおっしゃいました。
それは、対立だからです。誰にとっても、世界は自分(小宇宙)と自分以外の外の世界(大宇宙)という2つで成り立っています。
そうした視点で見たとき、極論を言うと、人がとるべき行動は3つあります。一つは支配、もう一つは服従、さらにもう一つは調和です。
支配というのは、外の世界を自分の意思で何が何でも動かそうとすることで、服従は外の世界から起こってくることを自分の意思を持たずただ受け入れること、調和は自分の意思をしっかりともちつつも外の世界の変化の流れに乗って柔軟に対応しながら世界とともに変化することです。
そして、井口師範は、調和に武道のあり方を見出し、そこから、相手を受け入れ、自分を中心として相手と共に動くことを合気道の極意としました。
そこで、相手と繋がり受け入れる「結び」という意識を重視しています。
結びを技術にしたのが合わせ
では、具体的に「結び」を行うにはどうしたらいいかという問題があります。
「結び」というのは、いわば意識です。相手と結びを作ろうと思っても、実際にどうやったらいいのか分からないのではないでしょうか?
その方法というのが、合気道では「合わせ」と呼んでいるものです。
先ず、合わせを行うポイントは次の通りです
まず、一つ目の対立しないというのは、心に対立が出来た時点で、概ね相手はこちらの意思が読めるようになります。ですから、相手を無理やり右に倒そうとすると、すぐさま相手は自分の意図を読んで右に倒れまいとします。
ですから、心に相手との対立を起こすことは合気道では最もやってはいけないことです。
次に、服従しないというのは、相手になすがままにされるということです。このような状態だと技を出すことなどできません。
よく「赤子のように、力をダランダランに抜きなさい」という人がいますが、このような腑抜けた状態であれば技は掛けることはできません。
元合気会の師範部長であった気の研究会の故・藤平光一師範の「力を抜きなさい」という意味を間違えて捉えた礼です。
最後に調和すると一言でいっても、どう調和していいのか分からないといわれそうですが、相手が静止状態だと静止した状態でまず相手と一体になることを考え、相手が動いている状態だと相手の動きに合わせて一体になることを考えます。
物理の世界では相対速度という言葉がありますが、相対速度とは、相手との関係性で、相手と自分の間の速度ということで、相手が動いていても、自分が同じように動いていると静止と変わらないということです。
例えば、電車の中を考えると、走っている電車は、外から見ると自分も相手も同じように走っているわけですが、自分達からすると電車の中は止まっています。
ところが、武道の場合、後退すると気が退くので、相手に追い込まれて、結局は相手にやられてしまいますので、実際は理屈通りいかない問題点があります。
そこで、次回はこの問題点を武道ではどう解決するかを話したと思います。
もしよければ、下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。
 にほんブログ村
にほんブログ村